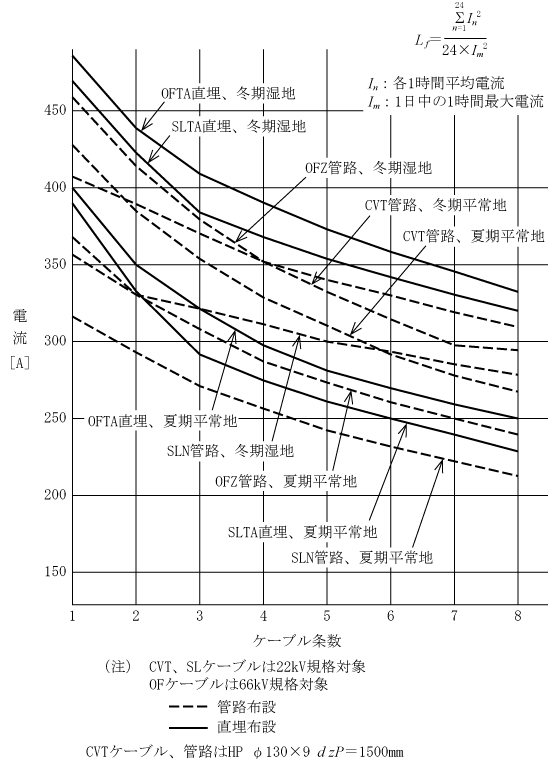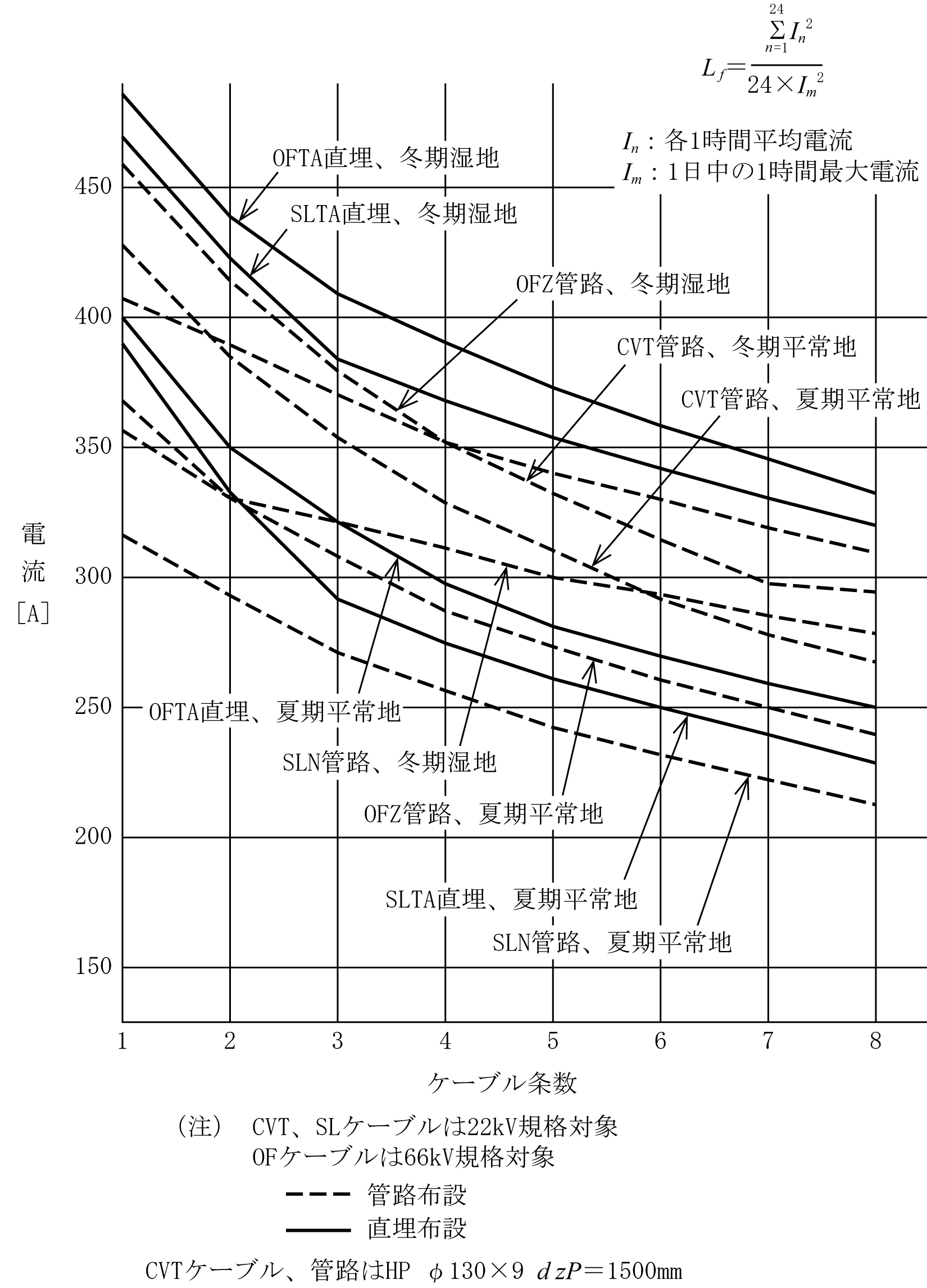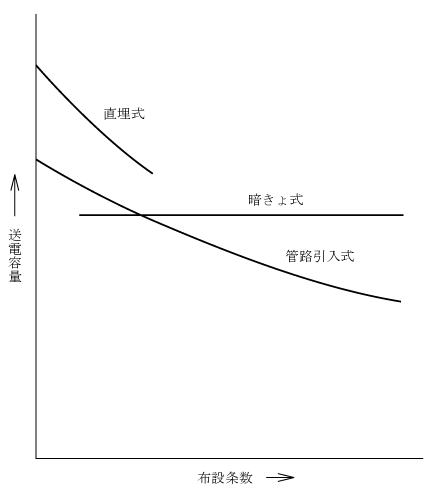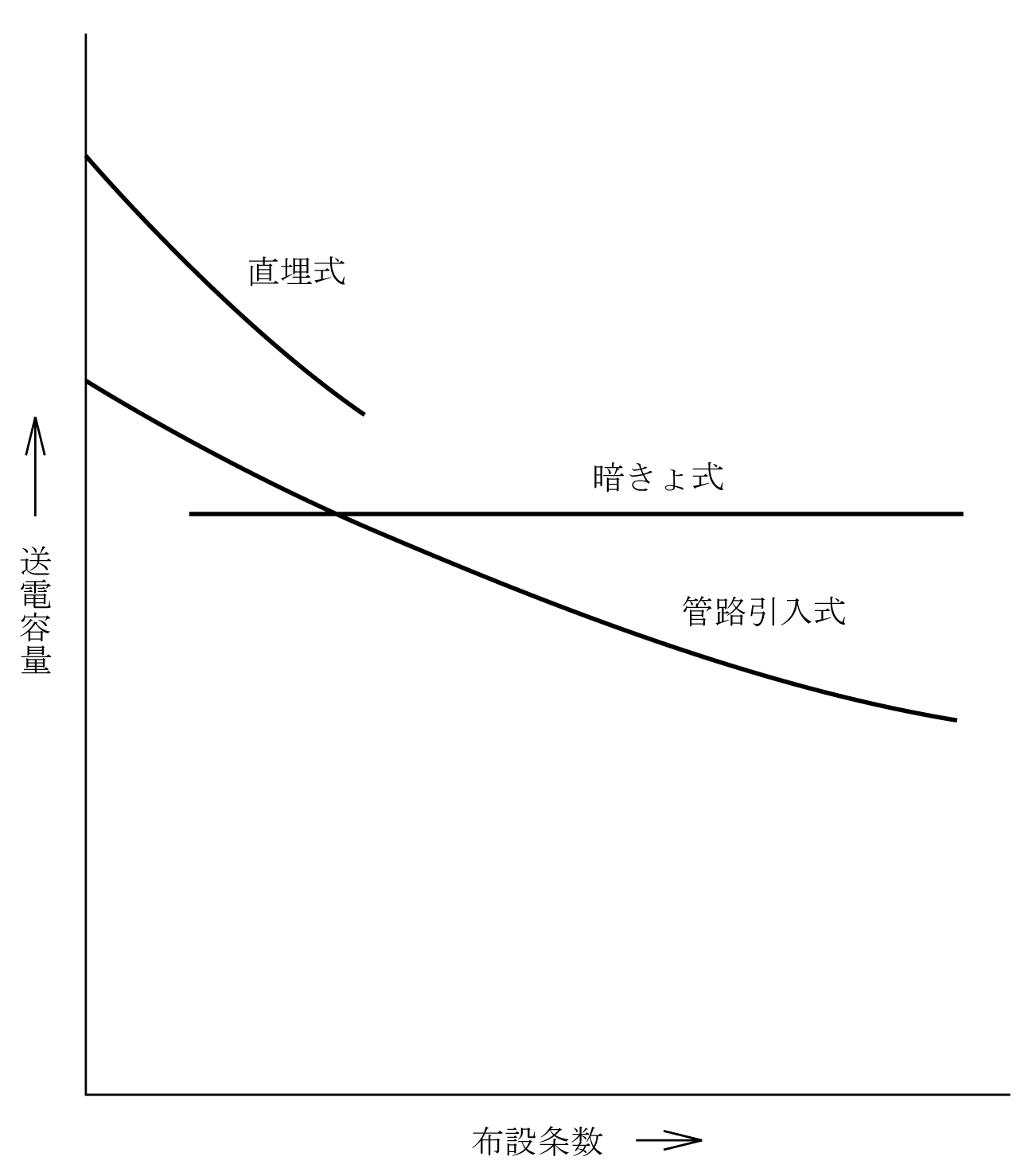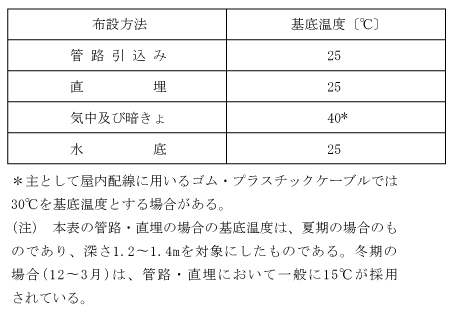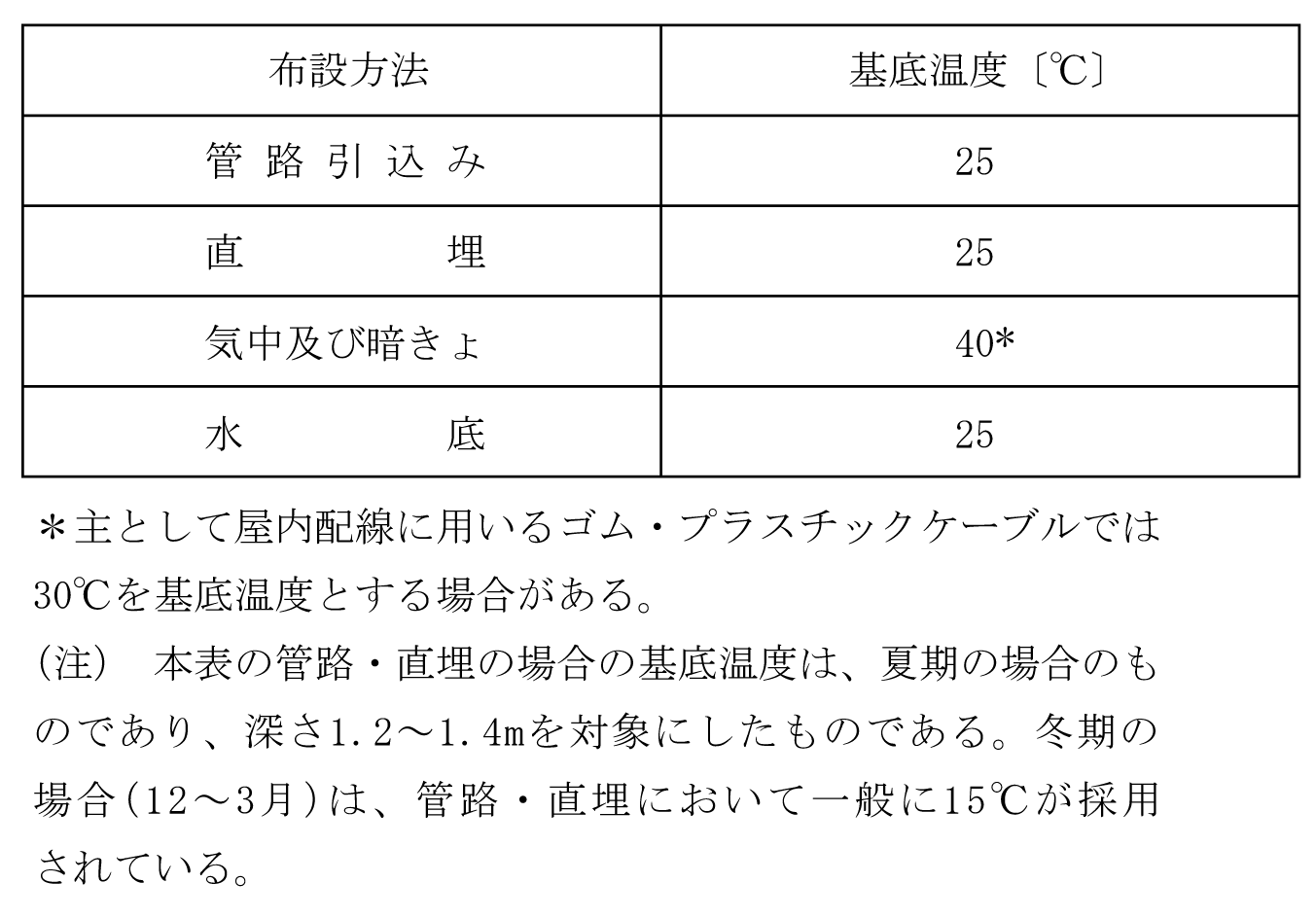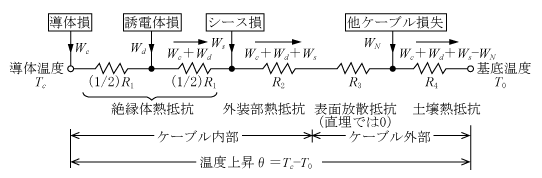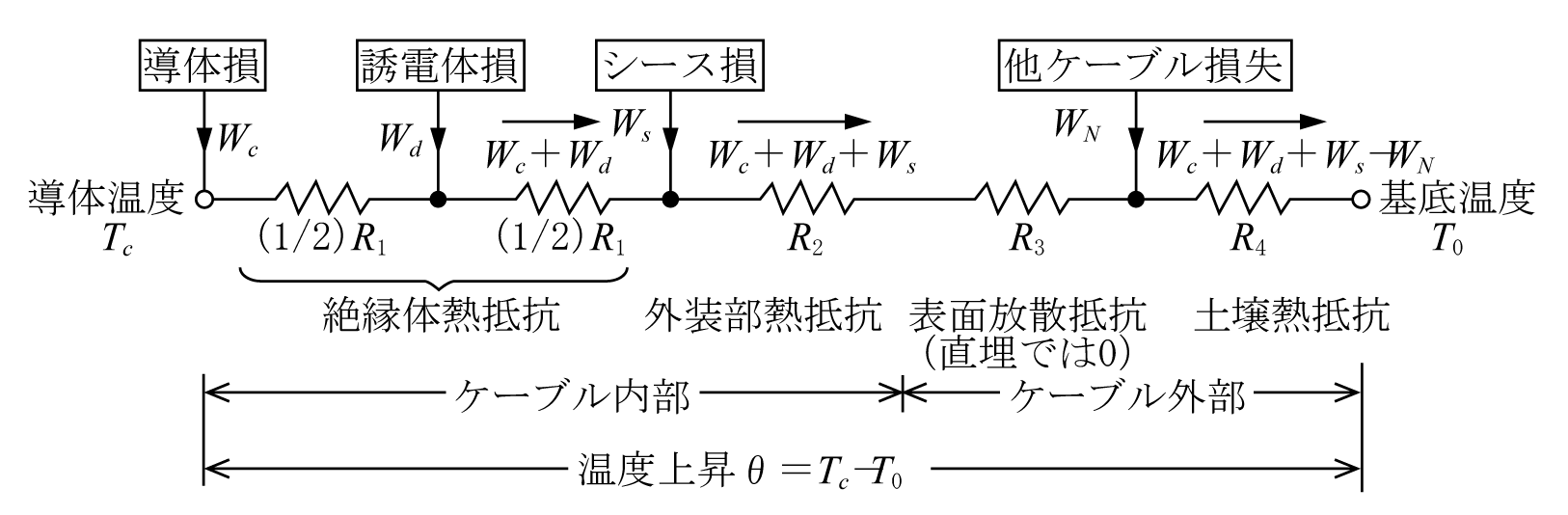〜終わり〜
■ぜひアンケートにご協力下さい■
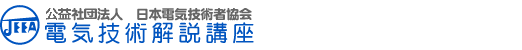

架空電線では電線相互の熱干渉が無視できるため、電線の素材とサイズが決まればその許容電流は定まる。
また、許容電流を決定する電線の最高許容温度は焼き鈍りによる張力の低下が発生しない限度で決められる。
これに対して地中ケーブルでは併設ケーブルの影響が大きく、更に埋設されている土壌の熱特性により大きく変化する。
また、電線の最高許容温度は絶縁体の熱的な特性から決められる。
絶縁の厚さなどケーブルの構造は電圧によって異なるので、同じ導体サイズでも電圧、ケーブルの種類によりその許容電流は異なる。
また、併設ケーブルや埋設土壌の影響が強いことから布設方式、併設条数によっても大きく変化する。
第1図に150mm2 3心ケーブルの電圧、ケーブル種類、管路布設と直埋布設における許容電流の例を示す。同一導体太さでありながら大幅に異なることが分かる。
また、第2図は布設方式による許容電流の違いを示した概念図である。
直埋式は土壌とケーブルが直接接触するため、熱放散が良く、許容電流は大きいが、布設条数は3条以下ぐらいである。
管路式では多条数布設が可能であり、かつ予備管路の布設により、将来にわたって増設、引替えが容易であり、最も一般的な布設方式であるが、条数の増加に伴う許容電流の減少が大きい。
暗渠(きょ)(洞道)式は洞道内部温度を作業条件などから一定範囲に保つため、多条布設による許容電流の現象が少ない。
普通の場合検討の対象となるのは常時許容電流である。これは連続して流すことのできる電流の限度である。この値は周囲条件により大幅に変化するが、6.6kVの線路では計算の煩雑さを避けるため、代表的な布設方式ごとに、ケーブルサイズ別にその値を一覧表にし、かつ多条布設の場合、布設位置による低減係数を掛けることにより便利を図ることもある。
高電圧ケーブルでは、送電電力〔kVA〕/電流〔A〕が大きいため経済的観点から個別に計算している。
許容電流は布設方式、併設条数などによる相違が大きいため、全長にわたって同一導体サイズとせず、例えば配電用変電所への地中送電線では、ほかの引出しケーブルと併設される電源変電所付近や、二次側の配電線ケーブルと併設される受電変電所付近など併設条数が多くなる箇所では、その部分だけに大サイズのケーブルを使用するか、布設方式を洞道式にするなどして全長にわたり許容電流の協調を図ることもある。
ケーブルの発生熱はその構造からその断面の半径方向だけに放散する。
常時許容電流を考える場合、ケーブルの熱容量は飽和しているので、温度上昇は熱流と熱抵抗の積になる。
これは熱流を電流、熱抵抗を電気抵抗、温度差を電位差(電圧)と置き換えれば、直流電気回路と等価と考えられ、熱オームの法則とも呼ばれる。
発生した熱は最終的にケーブルの存在に影響を受けない遠点に達する。その地点の温度を基底温度という。
基底温度は普通土壌では25℃(冬季15℃とする場合もある)、気中では40℃
にしている。基底温度を第1表に示す。
基底温度とケーブル各部の温度上昇の和が、ケーブル絶縁体の連続許容最高温度に達するときの導体に流れるときの電流が常時許容電流である。
第3図に電力ケーブル温度上昇の等価回路を示す。
許容電流に関与するケーブルからの発生熱には次のものがある。また、ここではケーブルからの発生熱の単位は〔W/cm〕とする。
(a) 導体損
導体に流れる負荷電流によるジュール損であり、3心ケーブルでは3倍になる。
(b) 誘電体損
絶縁体内部に発生するもので、充電容量と誘電体正接(tanδ)の積であり、電圧が印加されれば負荷の有無に関係なく発生する。したがって、誘電体損による温度上昇は負荷に無関係に一定である。
なお、誘電体損は絶縁体熱抵抗の中央に集中して発生するとして計算する。
33kV以下の架橋ポリエチレン絶縁ケーブルでは無視できる。
(c) シース損
金属被覆や遮蔽(へい)層に発生する損失で、単心ケーブルの場合に対象になり、CVTケーブルを含む3心ケーブルでは無視する。
シース損は導体電流に比例するので、導体損に増加率を掛けて計算する。
シース損はシースの接地方式により異なるが、一般には導体損の数%程度である。
(d)多ケーブルの損失
併設されたほかのケーブルの損失熱は、土壌の温度上昇を増加させ、土壌熱抵抗の増大と同じ作用をする。