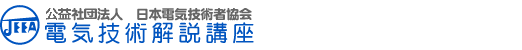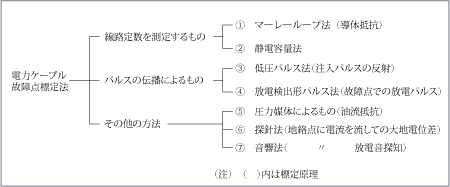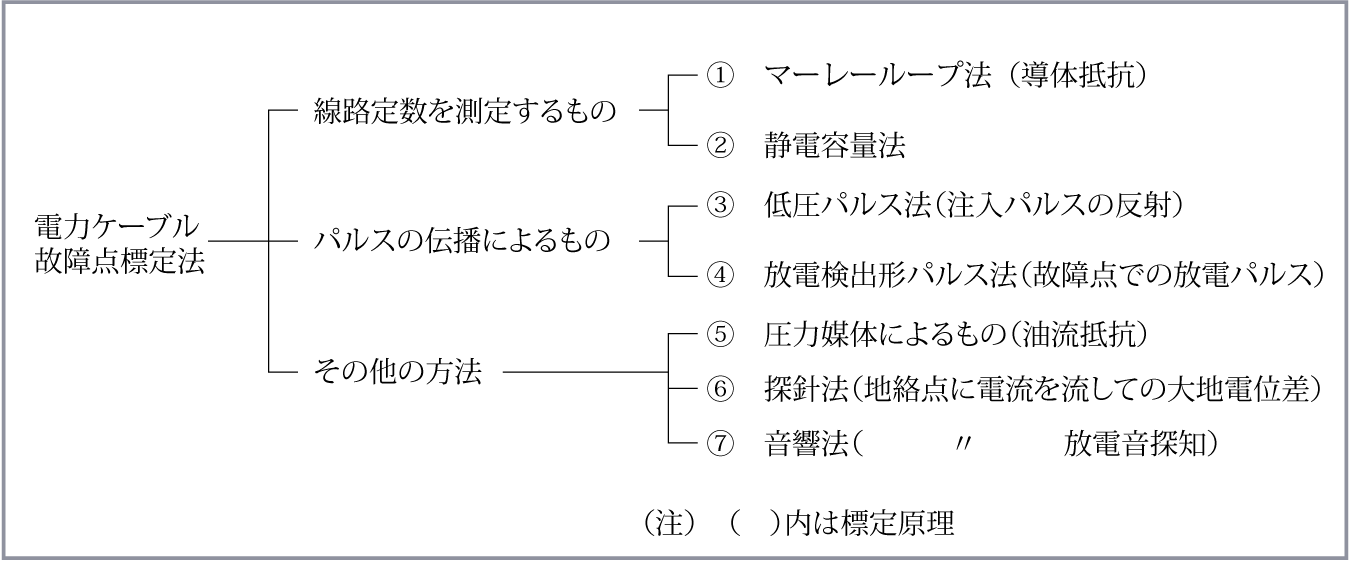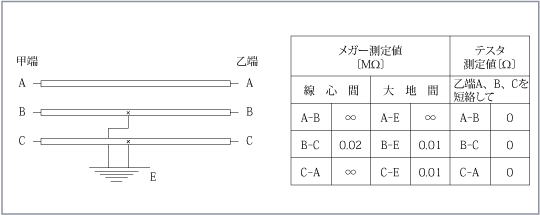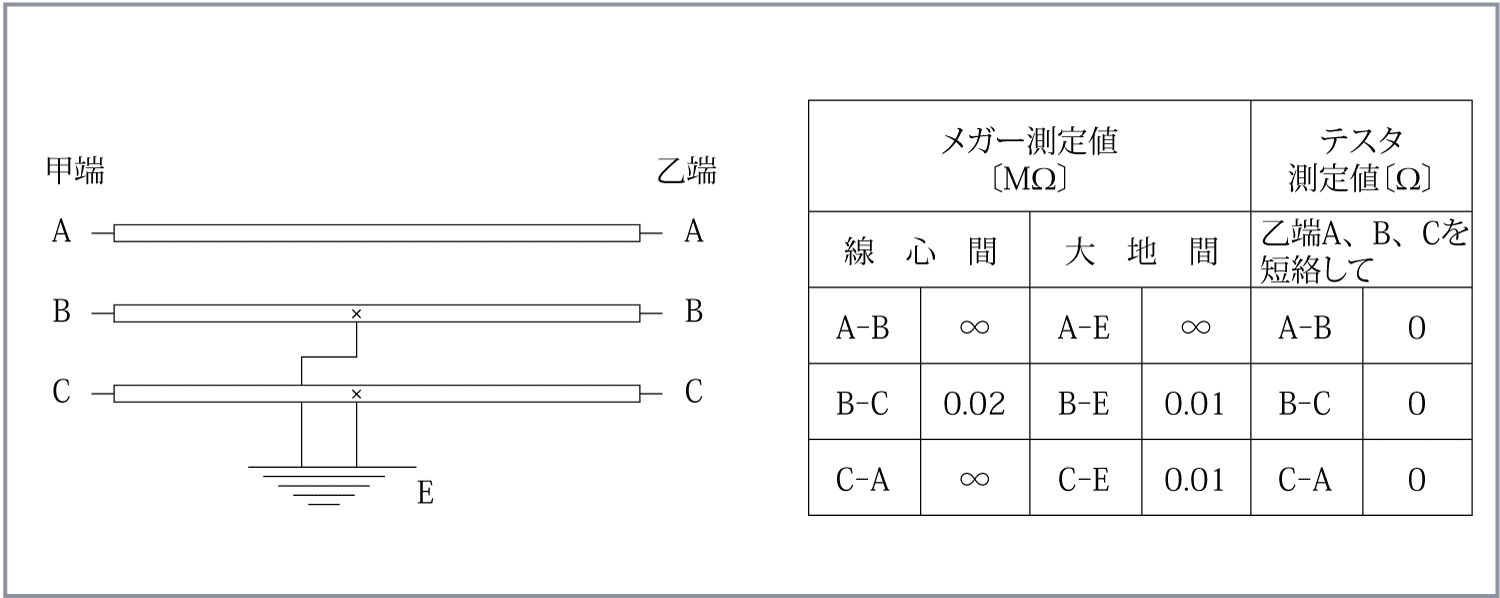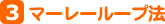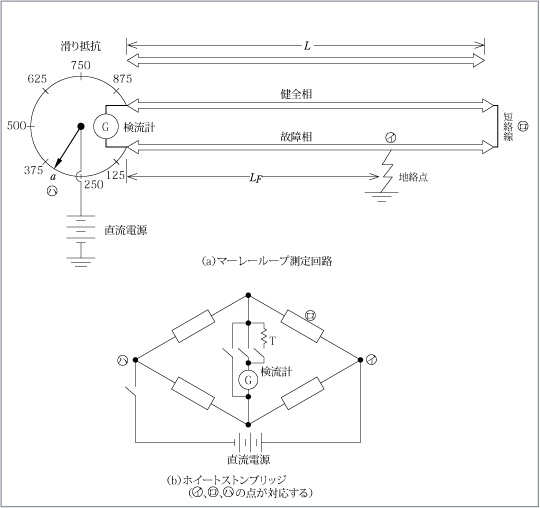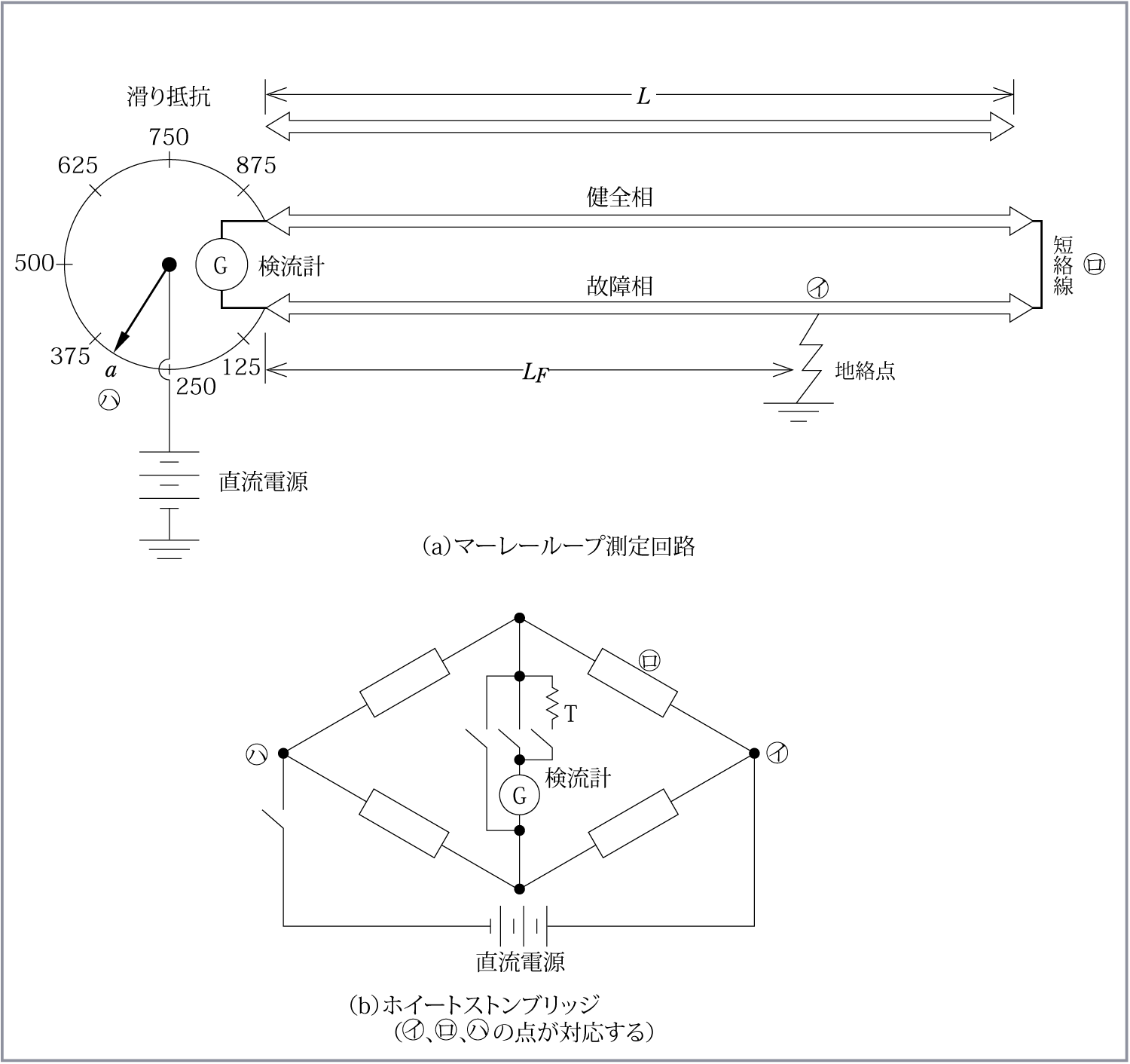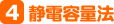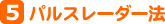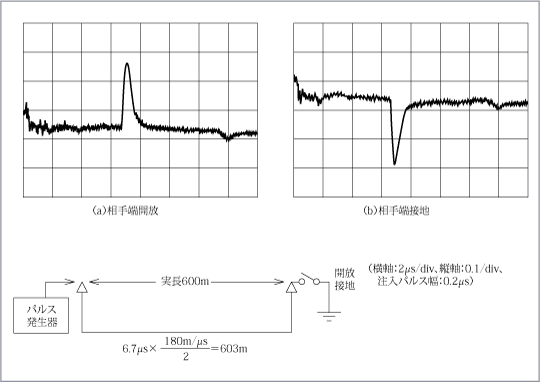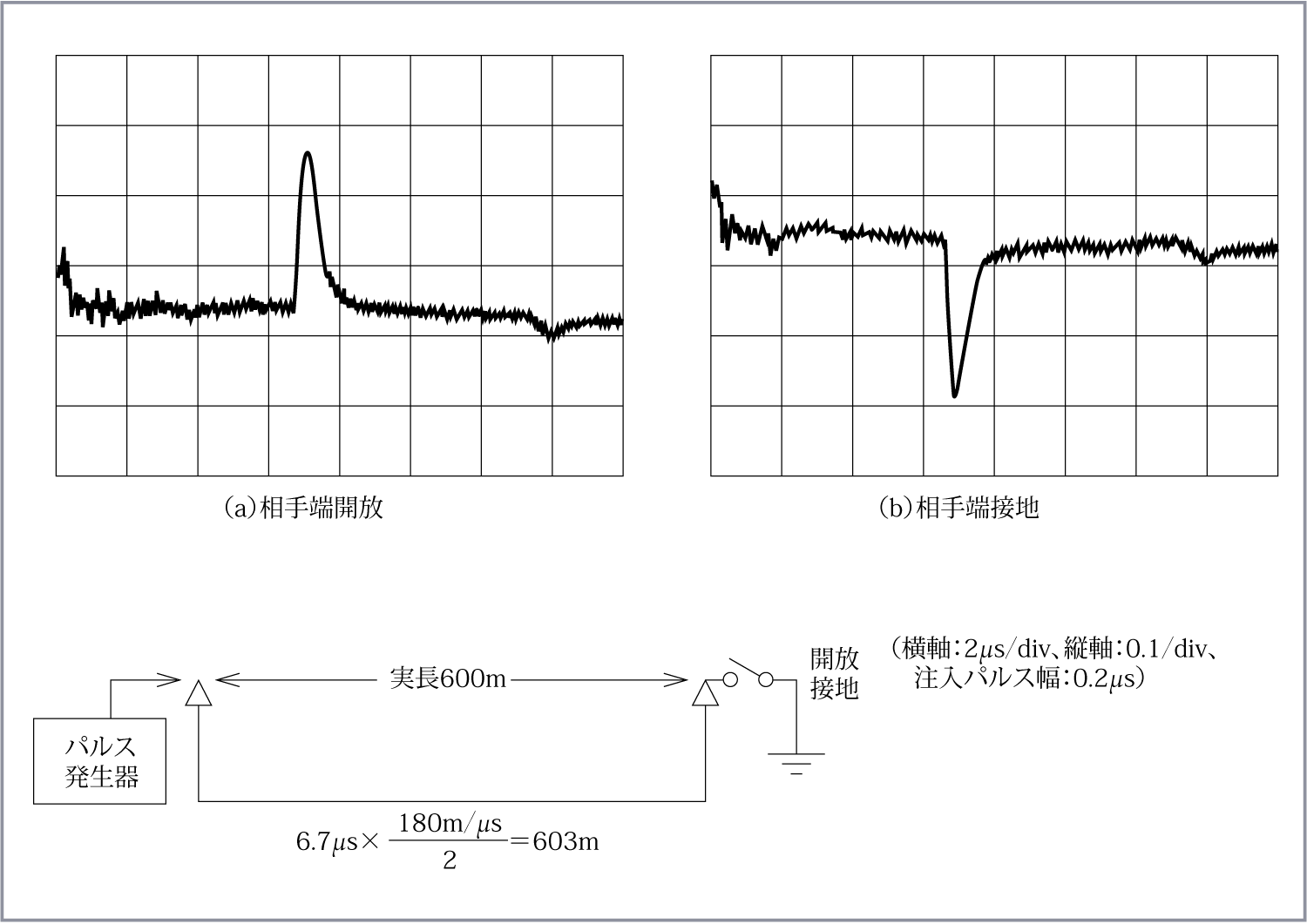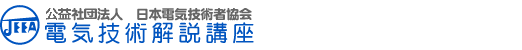



地中電線路は電線に電力ケーブル(以下、ケーブルという)を使用し、文字どおり埋設されているため、目視点検の可能な範囲はごく限られている。このため故障点の探査はほとんどの場合、端末からの各種測定によらなくてはならない。ここでは実際に行われている故障点測定法について説明する。
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your
Flash plugin.
※テキスト中の図はクリックすると大きく表示されます

地中電線路の故障点測定の最も一般的な方法は、故障点までのケーブルの線路定数と、全長の線路定数を比較するもので、これにはマーレーループ測定器と、直読静電容量計などがある。
次に進行波の伝播を利用した測定が広く行われている。これは故障点あるいは端末でのサージインピーダンスの変化による反射を利用し、伝播速度から距離を算出するもので、以上が一般的に採用されている。
このほかにOFケーブルなどでは絶縁油などの圧力媒体の漏れ量や圧力分布を測定して故障点を求めるもの、また故障点に電圧を印加して、ケーブルシース(遮へい層)の電位変化や故障点の放電音から探知する方法もあるが、これらは測定というよりも主として故障点の確認のために行われる。
ケーブル故障点の測定には測定するケーブルの実長に対する比を求める方法が多く、またそのほうが測定精度も高い。したがって、地中電線路では建設時の記録の管理は特に重要である。

ケーブルの故障は90%以上が地絡事故であるが、故障点が水場にある場合を除いて極めて高い地絡抵抗を示すことが多く、メガーリングでは健全相と事故相との判別が不能なこともある。これは絶縁厚さが数mmの間に地絡アークが集中するため、絶縁物が気化噴出して故障点で生成する炭化物を除去してしまうことや、その後のコンパウンドや絶縁油の浸出による絶縁回復のためである。この場合の故障点の等価回路は高抵抗と放電ギャップが並列になったものである。
特に特別高圧で受電する構内の高圧配電系統では地絡電流が小さく、故障がケーブルの表面まで達していないこともある。
また、最近の高圧以上のケーブルはすべて各相遮へい形になっているため機会は少ないが、短絡故障では断線になりやすい。
断線の場合には線間抵抗、断線極間抵抗、地絡抵抗が、それぞれ複雑に組み合わさっているため、測定に先立って各線間、大地間のメガーリング、及びテスタによる導通試験で故障の状況を把握しておくことが重要である。
特に断線の有無は測定方法の選択に根本的にかかわるため、慎重に確認する必要がある。このときメガーによる導通試験は厳禁事項で、思わぬ誤判定の原因になるため必ずテスタによらなくてはならない。第2図に2線地絡の状況確認測定の例を示す。
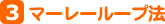
原理はホイートストンブリッジの変形であり、相手端でケーブルの健全相と地絡相を短絡してループとし、測定器の滑り抵抗と対応させたものである。第3図(a)、 (b)にマーレーループの測定回路をホイートストンブリッジの回路と対応させて示す。
図のような目盛配置のマーレーループで、目盛
aで平衡したとすれば、ケーブルの導体サイズが全長にわたって同一の場合、故障点までの距離
LFは次式で与えられる。
LF=2
aL/1,000 [m]
ただし、
L:ケーブル長[m]
異なる導体サイズのケーブルが混在している線路の場合はいずれか1種類の太さに換算し、測定位置によっては当該ケーブル部分を逆換算して実距離を求める。
マーレーループでは健全相があることが原則であるが、断線のない地絡相が1相あれば短距離の場合、補助線を健全相の代わりに使用して測定することができる。この場合の補助線はできるだけ測定ケーブルの導体サイズに近いものを使用する。
測定に必要な直流電流は50mA程度であるが、安定していることが必要である。地絡抵抗が不安定な場合は高電圧を印加して故障点の炭化を行う。これには意外に長時間がかかることが多く、結果として他の測定法に変えることもある。
ケーブルの故障は大部分が1線地絡であることから、故障点測定にはマーレーループが最も多く使用され、測定精度も誤差1%以下と高い。
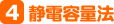
ケーブルの静電容量が長さに比例することを利用したもので、故障点ですべての
相が断線しているとき、断線していない相が残っていても補助線の設置ができない場合には、普通のマーレーループ法で測定することはできない。このようなときには静電容量法によると簡単である。
測定器としては市販されている直読型の静電容量計が便利である。測定端から故障点までの距離は次式で表される。
LF=
L×
CF/
CH (健全相がある場合)
LF=
L×
CF/(
CF+
CF0) (健全相がない場合)
ただし、
CF:測定端から測定した故障相の静電容量
CH:健全相の静電容量
CF0:反対端から測定した故障相の静電容量
この測定では測定端及び反対側で測定する相以外はすべて短絡接地して無用な静電容量が測定値に混入するのを防ぐことが大切である。
また、接地抵抗は静電容量と並列になるため、故障相が複数の場合には地絡抵抗の大きい相を測定対象としなければならない。この場合、地絡抵抗の許容値は使用する静電容量形の特性にもよるが、100Ω以上必要である。ケーブルの静電容量は電圧、種類、導体サイズで異なるが、0.3 〜 0.7μFであり、これから測定レンジを決める。
この測定は静電容量の比較測定であるから測定器の絶対精度はそれほど要求されず、測定操作もいたって簡単である。測定精度は地絡、短絡抵抗の値にもよるが、誤差1%程度と高い。
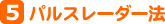
原理は故障相に繰返しパルス電圧を印加して、故障点でサージインピーダンスの変化により反射してくるパルス電圧をオシログラフで観測して、その往復伝播時間から故障点までの距離を測定するものである。主として断線故障の測定に採用される。
パルスのような進行波が線路上を伝播していくと故障点のようなサージインピーダンスの変化点で反射して戻ってくる。サージインピーダンス
Z1の線路から
Z2の故障点に進行波が到来したときに発生する反射波の大きさは次式で表される。
e’=
e0 (
Z2-
Z1)/(
Z1+
Z2)
e’:反射波
e0:到来波
したがって、ケーブルのサージインピーダンス(30Ω程度)よりも故障点のサージインピーダンスが大きければ正極性の反射波が、小さければ負極性の反射波が発生する。
また、故障点のサージインピーダンス(地絡、短絡抵抗)がケーブルのサージインピーダンスに等しければ反射波は発生しない。等しくなくても値が近ければ反射波が小さく、測定不能になる。第4図に説明のため、実長600mのケーブルの相手端を開閉してパルスを印加したときの実測図を示す。
図では伝播速度をケーブル内での進行波の代表速度とされる180m/μsとしているが、実際の測定では長さが既知の測定するケーブルで伝播速度を補正している。
故障点の算出は断線のない地絡故障では健全相と故障相の往復伝播時間の比で、断線故障の場合は静電容量法の計算で、静電容量を往復伝播時間に読み替えればよい。
パルスの波形は伝播中にひずむので往復時間の判読に熟練を要し、測定誤差も 1 〜 4%程度である。
また、マーレーループ法で測定不能な高抵抗測定用として、直流高圧を故障相に印加し、徐々に昇圧して故障点での対地放電によって発生するパルスを利用した放電検出パルス法もある。